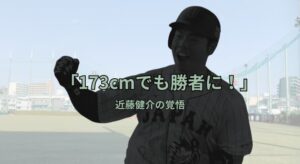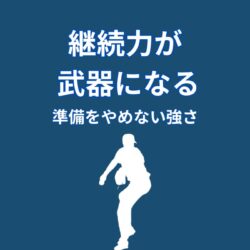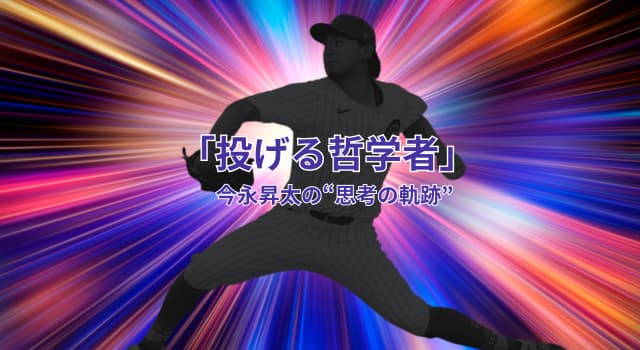
華やかなプロ野球の世界で、常に冷静さと知性を感じさせる投手、今永昇太さん。
試合後のコメントには、感情よりも「言葉の重み」が宿っています。
今永昇太選手が語る一言ひとことには、考え抜いた末に辿り着いた「自分の答え」がある。
その思考の原点は、実は高校時代にありました。
注目校でもなければ、派手な成績を残したわけでもない。
それでも今永昇太選手は、野球と真摯に向き合う「無名の時間」を、誰よりも大切に過ごしていたのです。
今永昇太の無名校・北筑高校から始まった「考える野球」

フォームは変わりませんね。
でも、考える野球はかわっているんでしょうね。
ついにこの2人が対決するのか。
←2009年 WBC胴上げ投手のダルビッシュ有
→2009年 北筑高校硬式野球部の今永昇太 pic.twitter.com/EYIhp70BHq— 牧スーゴ (@makisugo) May 2, 2024
今永昇太選手が通っていたのは、福岡県の北筑高校。
当時は甲子園の常連でもなく、全国的に名の知れた強豪校でもありませんでした。
だからこそ、練習環境や注目度では劣っていても、「考える力」を磨く時間がたくさんあったといいます。
そんな環境の中でも、今永昇太選手は早くからチームの中心選手として存在感を放っていました。
ストレートの速球と切れ味鋭い変化球を武器に、次々と打者をねじ伏せる投球。
そして3年生の夏の大会では、強豪校を相手に連続完封勝利を記録するなど、その実力を全国に示しました。
さらに打撃でもチームを支え、投打にわたるオールラウンドな力と、仲間を引っ張るリーダーシップが高く評価されていたといいます。
それでも今永昇太選手の真価は、単なる実力や結果だけでは語りきれません。
周囲が「とにかく投げ込め」と声を張る中で、彼は「どうすれば上手くなれるのか」を、静かに考え続けていました。
闇雲に努力するより、まず自分を観察する。
その姿勢こそが、後の「投げる哲学者」へとつながっていきます。
「怒られて終わり」にしない!高校時代から「考える習慣」

高校時代に走り込んだ
地元の公園だとか?
【メジャー今永昇太選手が「マンホールのふた」に “投げる哲学者”ソクラテスポーズ 高校時代走り込んだ地元の公園に 福岡・北九州市】
福岡県北九州市出身のメジャーリーガー今永昇太投手がデザインされたマンホールのふたが母校でお披露目されました。
— 福岡TNCニュース/記者のチカラ【公式】 (@TNC8chnews) June 20, 2025
高校時代の今永昇太選手は、監督に叱られても、落ち込んで終わることはなかったそうです。
家に帰るとノートを開き、「なぜ怒られたのか」「次はどうすればいいか」を静かに書き込む。
そこにあるのは、感情ではなく「思考」。
言われたことを受け流すのではなく、「原因と結果」を自分の中で整理して、次の行動へとつなげていきました。
その姿勢は、練習の取り組み方にも表れていました。
当時の監督・井上勝也先生(現・香住丘高校監督)によると、
「今永昇太選手がやっていたピッチャーのトレーニングは、全部教えたわけではなく、自分で調べて考えたものをコツコツ継続していた」といいます。
ウエイト器具に頼らず、鉄棒での懸垂や、綱を使ってトラックのタイヤを引き寄せるようなトレーニングで、体幹や背筋を地道に鍛えていった。
設備が十分でない県立高校という環境の中で、「今あるものでどう強くなるか」を考え抜く姿勢が、今永昇太投手の基礎をつくっていったのです。
この「考えるクセ」こそが、後に彼を支える最大の武器になっていきます。
今永昇太の高校時代は野球ノートが必需品

ノートに書いている?
今永昇太投手は、自分の投球だけでなく、試合全体を客観的に見ることを大切にしていたといいます。
「自分の調子」「相手打者の反応」「風の向き」
そのすべてを冷静に言葉でノートに記録していきました。
当時の野球部長・田中修治さんは、そんな姿をよく覚えているそうです。
「1年生の頃はノートを出さなかったりもしていましたが、試合に出るようになってからは内容がガラッと変わりました。
他の部員が「感じたこと」や「質問”」書く中で、今永昇太選手は違ったんです。
『こういうことができないから、こういう練習をした』
『今はこういう課題に取り組んでいる』
自分の弱点を具体的に分析して、次につなげようとしていたんですよ」
「今の自分に何が足りないか」を冷静に見つめる目。
この積み重ねが、ミスを恐れず修正できる「思考のリズム」を作り出しました。
野球を通して身につけた「分析力」は、大学、そしてプロの舞台でも光り続けます。
大学・プロで花開く今永昇太の「思考の野球」

どこから出てるのでしょうね。
今秋、ドラフト候補1位の駒沢の今永がようやく戻ってきました。
【150621】春は故障で登板なし。ドラフト1位候補左腕・今永昇太、完全復活を目指す秋 | http://t.co/XduXq8dKmh #大学野球
— ベースボールチャンネル (@base_ch) September 21, 2015
駒澤大学に進学すると、今永昇太選手はさらに「考える野球」を突き詰めました。
フォームの微調整、試合展開の読み、チーム全体の流れ、どれも「自分を知る力」が土台になっています。
そんな今永昇太選手にとって大きかったのが、西村監督の存在です。
選手の自主性を重んじ、適度な距離を置いて見守るスタイルのもと、今永昇太選手は後にこう語っています。
「高校のときも自分で考えて練習していたんですが、大学に来てもそうやって自分で練習メニューを考えてやらせてもらえたのが良かったです。
やらされてやる練習よりも、『自分がこういう選手になりたいからこれをやろう』と練習した方がはるかに力になると思う。
西村監督のやり方が、僕にはとてもやりやすかったです。」
「考える力」を育ててくれる環境の中で、今永昇太選手は「主体的に成長する喜び」を知っていきました。
そして、DeNAに入団してからも、その姿勢は変わりません。
「相手打者の呼吸を感じながら投げる」
「感情を乱さず、次の一球に集中する」
こうした言葉の背景には、高校時代から続く「思考の習慣」が静かに蘇っているように思えます。
今永昇太が「考える力」が導いた哲学と成長
今永昇太選手の言葉には、いつも「結果より過程を大切にする」哲学があります。
勝敗や数字よりも、「どう向き合ったか」「どう考えたか」を自問する。
その姿勢こそが、彼の投球に深みを与えています。
北筑高校での3年間は、努力や根性ではなく、「考える力」で成長を掴み取った日々。
どんな環境にいても、自分を見つめ直し、思考を積み重ねることで道は開ける!
今永昇太選手の高校時代は、そんな普遍的なメッセージを静かに教えてくれます。
まとめ
今永昇太選手の野球人生は、常に「考える力」とともにありました。
北筑高校時代、強豪ではない環境の中で、自ら練習を工夫し、叱られても感情ではなく「なぜ」をノートに書き出して整理する。
その習慣が、今永昇太選手の原点です。
駒澤大学では「自主性を重んじる指導」のもと、
「やらされるより、自分で考えて動く」姿勢を磨きました。
プロでも、感情を乱さず、相手の呼吸を読み、淡々と一球に集中する。
その冷静な姿はまさに「投げる哲学者」。
メジャーのマウンドで見せる静かな闘志の裏には、高校時代にノートを開いていた一人の青年の思考が、今も息づいています。